
ゴスフォードパーク [DVD]
監督はインタビューで、「犯人探し」を撮りたかったのではなく、どんな環境で殺人が起きたのかを描きたかったのだと言っています。
アガサ・クリスティーの原作を元にしてはいますが、推理サスペンスとは違います。犯人などもすぐに察しがつきます。 当時の、だんだんと時代に取り残されつつあった貴族社会の有様を描いた映画です。彼らにとってはよりいい、体裁のとれた暮らしを求めることが最重要事であり、殺人すら、結局はそんな日常の1コマでしかないのだという印象を受けました。 そして、何より特筆すべきは、召使たちの視点でストーリーが描かれていること。これまで、映画やドラマでイギリス貴族ものはいろいろ見ましたが、これは初めて見たタイプでした。仕事上の決まり事など、当時の生き!!証人をスタッフに招いて再現しているので、リアルです。殺人よりずっと興味をそそられますし、面白いです。 イギリス貴族屋敷の住人の隅々を、タイムトラベルして覗き見する気分。お好きな方はどうぞ。 
ゴスフォード・パーク (名作映画完全セリフ集スクリーンプレイ・シリーズ)
アカデミー賞脚本賞を受賞した、「脚本」です。
映画のよさは、ひとつは優れた脚本にあると思います。 この映画にはさまざまな階級の人々が出てくるので、言葉や言い回しの違い、ユーモアが沢山。それを知れるということは興味深い。 イギリス英語独特の表現も気になるところだ。 映画と合わせて読めば、理解が深まると共に、科白の深みが増す。 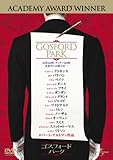
ゴスフォード・パーク [DVD]
イギリスの映画が好きでいつも買っています。この作品もすごく好きです。

ゴスフォード・パーク - オリジナル・サウンドトラック
パトリック・ドイルによる音楽は「いつか晴れた日に」「イースト/
ウエスト」と同じく前に出過ぎない静かな曲調が実に素晴らしいです。 また、出演者の一人ジェレミー・ノーザムの歌声もとても印象的です。 とても心地の良い歌声で、その上かなりの存在感があります。彼が演じ ていたアイヴォア・ノヴェロは有名な音楽賞の一つ、A・ノヴェロ賞と しても知られている、実在の人物なのですね。ノーザム自身、音楽家の 家庭で育ったそうで、それを知れば彼の才能も納得できる気がします。 私的には彼の事、俳優としてもとても好きなのですが、なぜ音楽界に 入らなかったのか、不思議に思わざるをえませんでした。それくらい、 映画に劣らぬ素晴らしい「作品」なので、自信を持ってお勧めします。 
ゴスフォード・パーク (ユニバーサル・セレクション2008年第1弾) 【初回生産限定】 [DVD]
ロバート・アルトマン最後のヒット作。1932年時点での英国貴族階級の風俗習慣を「観察」した作品。俳優陣がやたら豪華で時代考証が厳密でミステリー自体は(わざと)大したことはない、というのが特徴。
「英国貴族」ってのはいまやハリウッドへの輸出品のようですね。お時間があったら脚本家コメンタリーを聞いてみて下さい。彼自身、貴族階級の人らしい。えんえん貴族の悪口を言っています。貴族がいかに見栄っ張りで偽善的で傲慢で怠け者で金の心配ばかりしている集団か、それに比べて労働者階級の人々がいかに「現代」や「未来」と繋がっていたか等々。途中で肩をポンポンとして「もういいから…」とやりたくなります。 英国の貴族階級は19世紀末から衰退し出し、1930年代というとほとんど断末魔だったはず。第二次大戦後には相続税で息の根を止められて。そういう段階にある階級をことさら叩いて自己主張のネタにすることもないんじゃないの、と思うんですが、何がそんなに憎いんでしょう、この現代に生きるお貴族の脚本家さんは。しかも貴族生活の時代考証としてナンシー・ミットフォードの『Noblesse Oblige』を出してきてるあたりが怪しい。あの本はナンシー・ミットフォードが「貴族階級とは」ってテーマであくまで悪ふざけで書いて、売れたので本人が腰抜かしたって本のはず。貴族は茶を飲むのにミルクを先に入れるとか後に入れるとか、ナンシー・ミットフォードの冗談のはずだけど、この映画では大真面目に「貴族の習慣」として紹介されている。うーむ。ちなみにこの脚本家さんがアイン・ランドの影響を受けているらしいこともコメンタリーから知りました。 現代は輝かしい民主主義社会なので「貴族」は叩かなくてはいけない、しかし裏には大衆の根強い憧れもある、という構図が見え見えの、ある意味いやらしい映画。アイヴォー・ノヴェロの懐メロの数々が素晴らしかったです。 |

|
愛と哀しみの果て自由と孤独しか愛せない男、その男を愛してしまった女・・・】【アフリカの広大なサバンナに生きた女性の、愛と冒険のトゥルー・ストーリ... |
|
イギリス英語がきける面白い映画ないですか?ハリーポッター以外でお願いします。 【中古】ゴスフォード・パーク(DVD)<マギー・スミス、マイケル・ガンホン、クリスティン・スコット・トーマス、ライアン・フィリップ、ボブ・バラバン> 映画を探しています 以前にBS2で観た映画なのですが、 ・昔の外国の上流階級の屋敷... R指定がついている映画がこの中にありますか? 外国映画で「群像劇」といって思い出す作品は?人が多すぎて人物描写のつめが甘くな... 映画のタイトルを教えて下さい リース・ウィザスプーンの旦那さん 【中古】ゴスフォード・パーク <初回限定版>/マギー・スミスDVD/洋画サスペンス |

浜田理恵プリザーブドフラワー新作のご案内 :a little art flower:がってんホーム 
山田参助hajiband 10.愛の賛歌 
CONNECTERSカントリー・ロード(cover) / The Connecters 
砂原良徳16-bit SAD FINAL SECRET / 砂原 良徳 
和田慎二プロ襲来!火ノ鹿たもん先生と語る和田慎二先生の世界・その1 
則天武后名窯Fan de fan 白哥窯 則天武后から玄宗 楊貴妃 安禄山まで なぜ玄宗、アンロクは子に殺されたのか 
カルメン・マキカルメンマキ&OZ 復活!「午前1時のスケッチ」 
長谷川きよし灰色の瞳.加藤登紀子 長谷川きよし High quality |
[動画|ゲーム|ヤフオク]
[便利|辞書|交通]
[ランキング|天気|メル友]
[占い|住まい|ギャンブル]
南波杏 穗花 監獄壩子 女壩子當家 劇照
ゴスフォード・パーク ウェブ