
幻魔大戦 [DVD]
原作者や原作ファンの批判はどうであれ、原作を読まない私でも
楽しめましたし、今でも好きな映画です。
ルナや東丈が戦士に目覚めていく過程を細かく描いた前半パートが
特にいいですね。今はアニメでこんなに熱い映画、そうないですね。
音楽も良かったです。後半でやや勢いが悪くなるので星4つです。
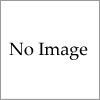
この「deep」は即ち「深・幻魔大戦」ということだろうが、再読を始めてみると、初めて読んだときほど東丈の描写やそもそもの文体に違和感がないのに気づいた。もっと「アブダクション」のような(つまりは「地球樹の女神」以降のか?)平井和正の「軽み」の部分が前面に出て、重みの部分は見えづらい、あっても続かない、文体になっており、東丈のキャラクターが直哉もどきになっている記憶があったのだ。
だが、ちょうど同時並行して「真幻魔大戦」を再読していたのだが、さほどの相違は感じられない読み始めだったのだ。
それが、一気に「アブダクション」度を加速したのは、“すてきなお母さん”雛崎みゆきが登場してからになる。彼女の登場以降、丈のキャラクターも世界の描写も「アブダクション」に“憑依”されていく。
が、にも関わらず、では雛崎みゆきというキャラクターがそれほどの圧倒的な存在感を持っていたかといえば……これは決してそうではないのだ。登場当初はそれなりの平井和正の女性キャラクターとしての魅力を備えているかに見える……が、振り子を丈に伝授することのみが役目であり、それが終わればもはや使命を果たしたかのごとく、急速に存在感を喪失していく。いてもいなくてもいい存在としか思われないのだ。(その証拠のように、続く「幻魔大戦deepトルテック」では消失している!)
この「deep」において、新しく登場した重要な女性キャラクターの中でも、雛崎みゆきほど重要であり、そして同時に存在意義のなかったキャラクターはほかにはいない。丈にとってすらも、最速で美叡(&美恵)や雛崎みちるに比べて、みゆきが占める割合はみるみるうちに失われていったのではなかったか。
平井和正作品の魅力のひとつには、確かに女性キャラクターの備える“女神性”があったはずだ。ところが、この「deep」で登場した女性キャラクターたちはいずれもかつての魅力に欠けている。東美恵たちなど、「真幻魔大戦」時の養女時代の愛らしさはどこへやら、といって虎4や杉村優里のようなパワフルな魅力を備えているわけでもなくという、どうにも感情移入する魅力の乏しい女性陣だったのだ。
「真幻魔大戦」登場時の美恵は、「東美恵子」だったはずで、それが“夢魔の寝室”編あたりから「美恵」になっているので、その辺ですでに世界が変わっていたのかも? 「美恵子」のままだったら、また違ったのかな? ……この辺は余談中の余談である。
丈のくだけた口調は、べらんめえ部分はともかく、GENKEN主催になる前の少年の丈にはちゃんと存在していたものなので、それほど違和感はない。それよりも、フロイのような“宇宙意識”とインフィニティたる“宇宙意志”はどう違うのか、振り子はコックリさんとは違うのか、そんな細かいあたりが気になってしまうところはある。
GENKEN時代の丈の失踪が、ついに逃避だったと断定されてしまったが、これはつらいところではあるかもしれない。
けれど、GENKENを作らないでいた丈のまわりにやはり久保陽子や平山圭子もいたようだ。彼女たちと一緒に、“非・GENKEN”の丈はいったいどう活動しようとしていたのか。その物語も興味が湧いてしまう。オヤブンでもなく、東丈先生でもない丈は、はたしてどう幻魔大戦に関わっていったのか。
そして……GENKEN世界の延長でありながら、ハルマゲドンの少女にはつながらなかったらしい世界の木村市枝は、「砲台山」の時同様、やはりあくまで木村市枝だった。それがやはり、純粋に嬉しいのが、どの読者にも共通のことではないだろうか。

新幻魔大戦 (秋田文庫 5-42)
最初は、なんじゃこりゃ、というのが正直な感想だった。
ストーリーは紆余曲折し、破綻し、しかも後半はマンガですらなくなる。
絵物語のような状態が延々と続くかと思えば、ラストの正雪とのバトルでまたマンガに戻るという、何とも捉えどころのない作品である。
本作が中絶した「マガジン」版「幻魔大戦」の後を受けた作品なのは、途中で名前の出てくるルーナや丈といった旧キャラで明かだ。
だが、しかし本書だけを読んだ場合には、その直接的な繋がりというのは分からない。
これから、というところで、本作もまた中断してしまう。
思うに幻魔というのは、人間が相手にするには大きすぎるものだったのだろう。
きつい言い方をすれば、平井氏のイマジネーションの限界、ということなのだと思う。
平井氏は「エイトマン」や「エリート」など、優れたSF作品の原作を書いている。
いずれも桑田次郎とのコンビというのが象徴しているように、多分SF的イマジネーションの強かった石森とのコンビでは、マンガのイマジネーションの強烈さに負けじと背伸びをしすぎたのではないだろうか。
桑田とこコンビでは、多分そのようなことが少なかったため、ある程度の完結を見ることが出来たのだろう。
思えば、本作でも石森の描く世界のイマジネーションはすごい。
近未来、江戸時代、超能力、そして幻魔の能力と登場人物の個性という、平井でなくても想像力を掻き立てられる筆力である。
すでに石森の筆はかなりデッサン力が落ちており、弟子の筆が相当入っているのが見え見えではある。
だが、その独特のタッチが不安定さと相まって、不思議な魅力を作っていることに、再読三読すると気がつく。
そして、破綻を内包したこのストーリーの魅力もまた、再読三読してようやく分かるのである。
犬神ものとの繋がりを、という原作のある意味贅沢な設定も、無理なくこなしつつ、ストーリーの必然へと融合する。
まさに危ういバランスの作品なのである。
惜しむらくは、原作者とマンガ家双方ともが疲弊してしまい、もしくは幻魔に取り憑かれたともいえるような、実に唐突な終わり方になっているということだ。
大変に残念なことであるが、石森氏による完成版は望めるものではない。

幻魔大戦 1 幻魔宇宙/超戦士 (決定版 幻魔大戦) (集英社文庫)
このタイトルから、混乱される人もいるかもしれませんので、少々解説します。
レビューしている、この「幻魔大戦」は、シリーズの四作目に当たります。
幻魔大戦シリーズの第一作目は、少年マガジンに連載された漫画の「幻魔大戦」です。二作目はSFマガジンに連載された「新幻魔大戦」です。
三作目はSFアドベンチャーに連載された「真幻魔大戦」です。70年代を舞台にしています。
そして、その真幻魔大戦を補完する目的で、野性時代に連載された第四作目が、この「幻魔大戦」です。これは本来、第一作目の「少年マガジン版/幻魔大戦」を完全小説化しようと目論んだものですが、途中からストーリーが大きく外れ出し、全く別の歴史を辿ることになりました。60年代を舞台にしています。
作者曰く「現代を舞台にした新しい救世主ストーリー」を目指したということで、自ら黙示録文学と呼び、その直接的な続編として、五作目に当たる「ハルマゲドン」が著されました。残念ながら、これは執筆を途中で止めています。
そして、70年代と60年代を結ぶかたちで描かれたものが、六作目にあたる「ハルマゲドンの少女」です。これをもちまして、第一期幻魔大戦は完結します。
肝心のレビューです。
この作品単体ではよく理解できないでしょう。なるべくシリーズの順番通りに読まれることをお勧めします。そして、20世紀末、ぼんやりした終末思想の広がった日本で多く読まれた作品だと思い馳せながら、読むと良いと思います。
救世主を中央に置きながら、救世主が活躍する前に物語が語られなくなるという、極めて奇々怪々な大長編SF小説です。日本における、不完全燃焼となった終末思想の、もしかしたら発端にある作品かもしれません。

e文庫 『ABDUCTION-拉致-』 平井和正
長い。
のは、特に問題ではないわけなのだ、実に。全20巻なら、平井和正の長編としては手頃なくらいではないか、という意識もある。
にも関わらず、こと「アブダクション」シリーズについては、これが各編1冊に収められていたら、もっと人口に膾炙できたのではないかという憾みもないではない。設定としてはかなり面白い気がする。未読だが、側聞による「ひぐらしの鳴く頃に」に先行しているわけだ。(違うかも)
「ひぐらしの鳴く頃に」が仮に想像したようなプロットだとして、異なるのはやはり「上書き」、そして謂わば輪廻転生の螺旋構造を同じ宇宙の回転で培っていく呪術師集団という図だろう。主人公・直哉の恋の数が全て女呪術師集団の結成のためにあり、そして直哉自身は小さな、そして大事な、ラムダのための行動に全てを集結させる。これが平井和正の独特さだろう。
キャラクターたちの面白さは変わるところはない。が、他の作品群と比べてベクトル感覚が欠如しているのは、視点が基本的に直哉ひとりであるのに主格が「少年は」と語られているところが大きいような気がする。同じように「少年は」が多用される「狼の紋章」では、青鹿晶子の視点が中心で、これに少年犬神明をハードボイルド的に外面から描く形で「少年は」と語られていた。そしてこれが同時に、突如として犬神明の懊悩する内面を描写する際のインパクトを産んでいたのだ。
もし「アブダクション」が、「直哉は」或いは「おれは」という通常の三人称もしくは一人称であれば、全く異なった印象の作品だったのではないだろうか。
「直哉は」と語れないのは、直哉が元猫ならぬ元武志だからだが、「少年は」とハードボイルドにどこか一枚別視点を通しての主格が殆どを占める全20巻は、平井和正の抜群のはずの感情移入の魔法を煙らせてしまったような観がある。フィルター越しになっているのだ。いつもの、主人公と思わず同化していくドライブが掛かっていかないもどかしさがある。
一人称「おれ」で語られていたなら、果たして「アブダクション」がどうなっていたか、興味がある。しかし、ここにはフィルター越しで感情移入を阻害せざるを得ない意味もあったのかもしれない。
トルテック呪術の特質は、「非情」――少年犬神明が希求して得られず、ゾンビー・ハンター田村俊夫が疑似体験して脱出した冷徹さが呪術師に不可欠な物であるなら、それは平井和正最大の武器を封印した作品のようになるのが当然だったのだ。
結果、アンリ・ベルトランとの対決は高揚する死闘になることもなく、そればかりか、せっかく生成した女呪術集団と青い宇宙の侵攻者との攻防もエンタテイメントであればそこにこそ筆を費やされるところが看過されている。これはこれで実に平井和正らしいところではあるだろう。
続く「その日の午後、砲台山で」の中で、一人称「おれ」として四騎忍が塚原組のヤクザ矢頭を叩き伏せるシーンなど、ウルフガイや幻魔大戦往時と変わらぬベクトルが走っている。だから、平井和正がベクトル疾走を喪失したわけではない。「アブダクション」では「非情」が描かれなければならなかったのだ。
そして、しかし、それは文字通りの情愛の喪失を尊ぶ物ではない。
だから、ラムダは無事に探し出されていたのだから。








