美術家の横尾忠則さんが先日(10月9日)、朝日新聞の書評で紹介されていた本です。
オリンピック史上初のマラソン2連覇を達成した選手とはいえ、名前を聞くのも初めてのような人物。
横尾さんの書評はアートや映画関係の本が多く、いつもなら書店で手にしてから購入するのですが、それでも読むことにしたのは「なんとも悲哀に胸痛む運命的な二人の生涯」という横尾さんにしては珍しいほど率直で屈託のない紹介文のせいでした。
本書では三つの死が描かれています。
最後は脳溢血で息を引き取るアベベ、翌年、アベベを寵愛したエチオピア皇帝ハイレ・セラシエは暗殺で非業の死を遂げ、さらに10年後、アベベとは親子とまでいわれた
スウェーデン人トレーナーのニスカネンは、エチオピアの土になりたかったにもかかわらず、その意に反して故国の町で客死するように人生を終えています。
自らの意志であれほど輝いていた3人、栄光の頂点にいた3人が、願いもむなしくやがて人生に裏切られようにして最期を迎えるどうしようもない寂しさ。読みおえたあと、フッーとため息をもらしてしまう切なさが、横尾さんの言う「なんとも悲哀に胸痛む運命的な二人の生涯」なのかもしれません。
大仰な悲壮感ではありません。生きることにつきまとう一種のあきらめの感情、あるいは透明な悲しさのようなもの、波瀾万丈の人生も一篇の走馬燈として語られる短切な哀れさ。人生に対する静かな徒労感に襲われたのもそのせいかもしれませんが、とはいえ本書の読後感はあくまでも心地よい疲労感です。
もちろん、本書はそれだけの本ではありません。
無名の貧しい黒人青年がその才能を開花させて世に出て行くけなげさ。レース前、名前もろくに読み上げてもらえなかった
ローマオリンピックで、世界の強豪をつぎつぎと抜き去り、奇跡のようにして勝ち得た金メダルの衝撃とその意味。試合前の新聞記者の嘲笑は一転して、上を下への大混乱に陥ります。本当に胸のすくような快感です。
夜の闇(
ローマ大会のマラソンは夕方にスタート)のなかをたいまつの火にかざされながら走るシーンあたりから、本書もスピードを一気に高め、ページをめくる手ももどかしく感じる勢いで東京オリンピックへとどんんどん進んでいきます。快い読書の速度感と高揚感ですが、それだけに得意の絶頂で待ち構えていた悲劇への転調が際立ちます。
原作はイギリスですが、イギリス人ではなく日本人のためにかかれたような本かもしれません。東京オリンピックでは銅メダルだった円谷幸吉選手の自殺についても書かれており、ゴール直前に円谷選手を抜き去ったイギリスのヒートリー選手がこのときのレースについてインタビューに応じています。

 アベベ・ビキラ 「裸足の哲人」の栄光と悲劇の生涯
アベベ・ビキラ 「裸足の哲人」の栄光と悲劇の生涯
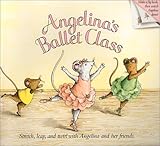 Angelina's Ballet Class (Angelina Ballerina)
Angelina's Ballet Class (Angelina Ballerina)
 Vitantonio(ビタントニオ) マイボトルブレンダー ストロベリーVitantonio VBL-30-ST
Vitantonio(ビタントニオ) マイボトルブレンダー ストロベリーVitantonio VBL-30-ST
