
勝手にしやがれ [DVD]
現代の芸術的作品にも通じるセンスを感じさせる編集と音楽の選び方。
一方で、ストーリーは泣けてくるほどつまらなく、見ているのが辛いほど。 ネオリアリスモの作品は未だに見ても面白いことを考えると、「旬があった映画」だったのではないだろうか。 映像作成に携わる人はお勉強として見る必要があるのではないでしょうか。 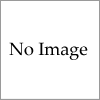
勝手にしやがれ【字幕版】 [VHS]
久しぶりに見ました。ですが今見ても全然古さを感じさせないところがすごいですね。それどころか見るたびに新しい発見があります。ごく単純なストーリーの底に普遍的なものが流れているからなのでしょう。この映画に代表されるような常軌を逸するほどのやさしさを持った男はフランス映画によく出てきますが、悲しいことに女にとってはそのやさしさが疎ましくなるときがあるのですよね。しかしこの男はほかの誰もが出来なかったことをやってのけました。それが「不老不死で死ぬ」ことだったのです。それはまさにこの映画が長年見つづけられているということで証明しています。
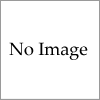
勝手にしやがれ
実際この中のフレーズを使ったところ大笑いされました。
ミッシェルの台詞は気障でパトリシアはそもそも英語訛りで文法に所々間違いあり。 映画自体新しい試みだったのでフランス語の勉強という訳には行きません。 というかゴダール全般そんな感じです。 この映画がすごく好きな人しか読んでも面白くないでしょう。 
勝手にしやがれ [DVD]
「息ができない」という意味の原題は、「海も山も都会も田舎も好きじゃなかったら息ができない」と最初に車のなかで銃を振り回しながら口ずさむベルモンドの自由への旅立ちの言葉。「空気が足りない」と言って殺しを犯したラスコーリニコフ(ドストエフスキー『罪と罰』)や「太陽のせい」と往って不条理な殺しを犯したムルソー(カミュ『異邦人』)に習って、ミシェールもきちんと警官殺しをやってくれる。
パリでの撮影はハンドカメラによるお手軽ロケみたいなシーンばかりで、ハリウッドもののように室内に三脚を立てて撮らないのだな、と思いながら見ていた。それはやはりパリが絵になるからなのだと思う。モノクロの映像の中でも、凱旋門を中心とした道路とそこを行き来する車の流れ、建築物の荘!重さ、夜のヘッドライトの流れと瞬き……ゴダールはやはり、とことん映像作家なのである。 ミシェールは生まれついての犯罪者であり、それがロミオとジュリエットのように国籍も育ちも、住む世界も違う、そんな娘に惚れちゃったばかりに悲劇を呼ぶという、何となく説明のつく落ち着きのいい話になっていると思う。女性に惚れ、女性に棄てられると死を選ぶ。無軌道というよりは、すべてか無、生か死かの世界だ。あまりにも刹那的で明日なき世界。孤独でやるせない物語なのだ。 ハンフリー・ボガートに憧れ、ルノワールには目もくれない。音楽は嫌いだが、女は好きで、始終煙草を吸っては煙を吐き出して空気をかきまわしている。これじゃあ息ができないわけだ。言葉と映像のキャッチボールがとても面白い!というのも、ゴダールの特徴みたいである。 |

北海道新聞北海道新聞「世界から疑念を持たれたという政治責任をどうとるつもりか」 
則天武后名窯Fan de fan 白哥窯 則天武后から玄宗 楊貴妃 安禄山まで なぜ玄宗、アンロクは子に殺されたのか 
シムーンシムーン(ピアノソロ) 
玉木宏【无字幕】日剧交响情人梦NG花絮 
難聴健康21 35 難聴の原因、予防と治療 その1 
エンリケ・イグレシアスEnrique Iglesias - Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona 
トルクレンチオートバックス トルクレンチ 
シザーハンズ日曜洋画劇場 / シザーハンズ |

[動画|ゲーム|ヤフオク]
[便利|辞書|交通]
[ランキング|天気|メル友]
[占い|住まい|ギャンブル]
【エピックミッキー】ミッキーと大冒険!実況プレイ パート8
勝手にしやがれ ウェブ

